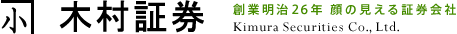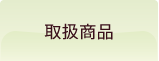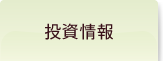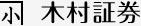ドル円相場の現状と今後の動向 (2016年3月版)
先月号の当コーナーで昨年からの株価急落の要因は「高すぎた事の反動」としており、米国の名目GDPに対する株式時価総額の比率や原油価格の問題等にふれている。その後も株式市場の乱高下は続いているが、経済の前提がいくつも変化しており、新しい秩序に対応するために市場が戸惑っている面もあると推察している。今月号では大きく変化した「ドル高円安の反転」の背景と影響、今後の動向について述べたい。
相対的購買力平価とは一時点を起点として、その後の当該国間のインフレ格差から時系列的に物価を均衡させる為替相場を算出したものであり、一物一価の思考が根底にあるものだ。今年1月時点でも円安の継続を予想する見方が多かったが、国際通貨研究所が毎月、発表しているドル円相場の購買力平価(1973年基準、企業物価ベース)は、昨年12月で「99円53銭」の水準であった。
相場を予想する際、最も陥りやすい間違いは矛盾している事が予想外に長く続くため、現状を当然とみる先入観が定着し、矛盾を前提とした予想をしてしまう事であろう。購買力平価は短期的には大きくかい離する事もあるが、120円を大幅に上回る円安は余りにも行き過ぎの水準であったといえる。ドル円相場は2月11日にロンドン外国為替市場で一時110円台をつけているが、円安の修正は一気に進展した状況だ。今回のドル円の急変は購買力平価の理論値に収れんする圧力が発生した事で起こったと思われる。相場の世界ではいつもの事だが、『矛盾の反動の発生時期』を予測する事の難しさを改めて痛感している。
いずれにせよ、ドル高円安の「高すぎた事の反動」が発生した事で、株式市場はどのような影響を受けたのであろうか。それは結論からいえば「膨らみ過ぎた円の表示額の収縮」が起こったと解釈している。日経平均株価の昨年の高値(終値ベース、以下同じ)は6月24日の20868円03銭であり、今年2月12日の14952円61銭の安値まで『28.3%』下落している。
これに対して日経平均株価をドル円相場(日本銀行公表、17時時点)で割った「ドルベースの日経平均株価」は昨年4月28日の168ドル53セントの高値から、今年2月12日の133ドル31セントの安値まで『20.9%』の下落にとどまっている。世界の株式市場の中で日本の主要平均株価の下落率が大きいため、株式に対して過剰に警戒する見方もあるが、ドル高円安で円ベースの表示金額が膨張し、円高への反転で同表示金額が収縮した事で、株価の下落率が拡大した面もあると思われる。対GDP比の米国株式時価総額、高価格の原油相場、そしてドル高円安、この「三つの膨張」に対する反動の調整圧力が、日本の株式市場を急落させた主因だと推察している。
先月号で述べたように米国の株式時価総額や原油価格の調整は相当進んだ事から、あとはドル円相場の落ち着きどころが今後の株式市場を読むうえで重要なポイントであろう。
ドル円相場の重要な決定要因の一つとして「日米の金利差」が挙げられる。米国の10年国債流通利回り(年平均ベース)のピークは1798年(7.6%)、1814年(7.6%)、1861年(6.5%)、1920年(5.3%)、1981年(14.2%)になっている。1814年を除けば「1798年から1981年まで」、ほぼ60年周期で米国の長期金利はピークを打っている。長期金利のボトムは12年7月の1.39%になるが、米国は昨年12月、9年半ぶりに政策金利を引き上げており、米国の金利は長期にわたって上昇すると予想している。
これに対して、日本銀行は2月16日に金融機関が保有する日銀当座預金の一部に0.1%のマイナス金利の適用を実施しており、日本の長短金利は急落している。ドル円相場に大きな影響をもたらす日米金利差は拡大する方向にあり、基調としてはドル高円安の圧力がかかりやすいといえる。
しかし、原油など資源価格の下落等で日本の経常黒字は大幅に拡大しており、ドル円相場はファンダメンタルズと日米金利差の綱引きの状況だ。日銀によるマイナス金利の導入は購買力平価の円高水準にシフトする圧力を緩和する強い効果があると推察される。『設備投資の国内回帰の定着、デフレの完全克服』を実現するためにも110円を上回る円高は阻止する必要がある。日銀の機動的な金融政策の発動を期待している。
(北川 彰男)