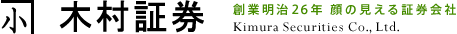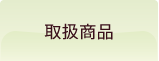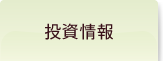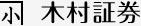加速する少子化の流れ (2021年9月版)
米国では景気・雇用の回復が進み、株価が最高値を更新する中、感染者数の拡大や自然災害を背景に、日本の株価はマザーズ指数はじめ停滞を余儀なくされている。
新型コロナウィルス感染症を背景に、少子化の流れが一層加速している。2020年の出生数は、84 万832 人と戦後最少を更新した。厚労省による今年の妊娠届け出数が前年比4.8%減少からすると、21年は80万人を割る可能性もある。コロナ禍以前より続いているこの流れは、経済成長、国力低下の要因として立ち塞がろうとしている。
日本の総人口は、昨年末1億2,571万人。内訳は年少(0~14才)1,503 万人(12.0%)、生産年齢(15~64才)7,449 万人(59.3%)、65才以上3,619 万人(28.8%)となっている。国立社会保障・人口問題研究所の推計では、総人口は、30年後に1億人を割り、45年後には9,000万人を割ると予想されている。また、国連推計による世界の年少人口割合が25.4%に対して、日本はその半分にも届かない。出生数は過去、第1次ベビーブームの1949年に年間約270 万人、第2次の73 年に約210 万人であった。しかし75年に200 万人を割り込んだ以降は減少を続け、84年には150 万人を割り込んだ。91年以降は、増加と減少を繰り返したのちに緩やかな減少傾向を辿り、2019 年に86 万5,239 人と90万人を割り込んでいる。
少子化の要因については、経済的、社会的状況など様々な問題が存在すると考えられている。未婚化・晩婚化など結婚に関するものや、ワーク・ライフ・バランスに対する両立支援の不足、若者の就業環境の不安定化などである。政府は、90年代のエンゼルプラン策定を皮切りに、少子化社会対策基本法(03年9月)、子ども・子育てビジョン(10年1月~15年3月)、少子化危機突破のための緊急対策(13年6月)、ニッポン一億総活躍プラン(16年6月)、「働き方改革実行計画」(17年3月)など、30年にわたり内容・規模を手厚くしつつ少子化対策に取り組んでいる。少子化の要因が複雑に関係しあうことに疑いはない。なかでも安定した就業や豊かな経済生活などの将来に対する期待が、結婚や子供を持つことを促す大きな要因と考えられる。しかし、将来の経済成長や不安定な働き方など、若者の将来に不安を抱かせる現状では家族形成への意欲が乏しいのも無理はない。そんななかで追い打ちをかけたのが、今回のコロナ禍による不安といえよう。
コロナ禍は、婚姻などに少なからず躊躇や影響を及ぼしている。政府も、結婚・子育て世代に与える影響を注視し、安心して結婚、妊娠・出産、子育てができる環境整備、対応を行なった。しかし、婚姻件数は19年に「令和婚」の影響で7年ぶりに増加したが、20 年の累計(速報値)は53万7,583組と前年同月比12.7%減少、1950年以来の減少率となった。出生数も、20 年の累計は過去最低となった。
コロナ禍による社会生活の変化が定着すれば、長期的には少子化の流れを弱める可能性を持つことも考えられる。テレワークの普及による柔軟な働き方や、通勤時間の減少は、生活バランスの改善を促し、家庭で夫婦が共有する時間の増加が男女の役割分担に関する考え方を一歩先に進める可能性を残す。
少子化による経済社会への影響は、以前より指摘されている。若年層比率の相対的低下が技術進歩を遅らせ、生産性低下を招き、経済成長の足かせとなる懸念である。また社会保障や税制を含めた負担の増加が、地域的な人口減少・高齢化、過疎化問題の偏在を起こしうる。政府が家族向け支出を増やし、出生率を高める対策を実施する以外にも、若い世代に財源を向ける仕組みづくりの必要性も考えられる。
しかしながら、少子化対策によって人口減少のスピードを緩めることは可能でも、その流れを止めることが難しいのが現状である。将来に対する不安が子供を持つことをためらわせる大きな要因とすれば、国の少子化対策に頼ることにも限界が予想される。社会全体の意識や行動が変わっていくことが、この流れを食い止める根本とすれば、もっと大きな改革が必要かもしれない。
(戸谷 慈伸)