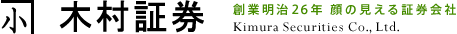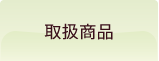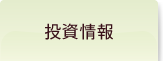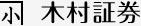米国株の本格的下落は何時になるのか (2018年11月版)
米国の戦後の景気循環は現在、第12波動になり、2009年2月から18年10月まで、景気拡大は112カ月になっている。第1~11波動の平均拡張期間は58.4カ月、平均後退期間は11.1カ月になる。12波動は既に第5波動の106カ月を抜いて、最長期間である第10波動の120カ月を抜く可能性が高くなっている。現在、米国の株式市場は最高値から下落しているが、再度反発すると予想している。株式市場は企業利益のすう勢に強い影響を受けるが、企業利益の伸びは景気の拡張期間に影響を受ける事になる。米国株が本格的な下落相場に転じる『きっかけ』は何になるのであろうか。今月号の当コーナーでは、米国の景気拡大の終了時期と米国株の本格的な下落相場の時期について推察したい。
国債の流通利回りは償還期間の長い方が、金利変動リスクが高いため、2年物国債よりも10年物国債の金利が高くなるのが、通常の状態だ。しかし、景気の過熱感が薄らぐなど政策金利上昇の必要性が後退した場合、中央銀行は同金利の引き上げを終了する事になる。その場合、国債の保有者は将来の金利低下に対処するため、償還期間の短い国債は売却し、長めの国債を買って高金利を確定する動きが強くなる。債券の流通利回りは売れば金利が上昇し、買えば金利が下がるため、2年物国債が、10年物国債の流通利回りを上回る「長短金利の逆転」が実現する事になる。
以上の観点から、資本取引の自由化進展で、世界規模の巨額マネーが米国の国債市場に流入するようになった80年代以降、米国の景気循環時の「最初に長短金利が逆転した時期、FFレート(米国政策金利)の上昇終了、景気の天井時期、金利逆転の景気天井への先行期間」を調べた場合、以下のようになっている。第9波動(景気拡張、82年11月~90年7月)、長短金利逆転88年12月、FF上昇終了89年4月、景気の天井90年7月、同先行期間「1年7カ月」だ。同様に第10波動(同、91年3月~01年3月)は、00年2月、00年5月、01年3月、「1年1カ月」。第11波動(同、01年11月~07年12月)は、05年12月、06年6月、07年12月、「2年」になる。
第9~11波動時で、「長短金利が逆転した時期がFFレート上昇終了に先行した期間」は、第9、4カ月、第10、3カ月、第11、6カ月になり、平均では『4カ月前』だ。また、2年物が10年物金利を逆転した時期から景気の山までの期間」は、平均すると『1年7か月後』になる。FFレートの打ち止め時期は諸説あるが、仮に同時期を「19年6月」と想定し、前述の平均の数値を適用した場合、長短金利の逆転は19年2月、米国景気の山は20年9月になり、過去最長の135カ月の景気拡大になる可能性もある。
次に景気のピークに対して、株価のピーク(米国主要平均株価指数・S&P500ベース、以下同じ)の先行期間は第2、6カ月、第3、12カ月、第4、8カ月、第5、13カ月、第6、10カ月、第7、マイナス1カ月、第8、8カ月、第9、0カ月、第10、12カ月、第11、2カ月になり、平均は『7カ月』になっている。前述の平均値で米国景気の山を20年9月とした場合、第2~11波動の平均で株価のピークは景気のピークに7カ月先行している事から、平均ベースでは株価の天井は20年2月になり、まだ、株価の上昇は相当な期間続くという想定も成立する事になる。
ただ、これは平均値で推測したものであり、株価は「経験則や平均値」で変動すると思い込んで、何度も手厳しい目にあった嫌な記憶もある。「まだはもうなり」という相場格言もあるため、もう一ひねりして考えてみたい。米国株の最大の懸念材料はGDP対して、時価総額(NY証券取引所・ナスダック市場の合計、年末ベース)の比率が高すぎる事だ。米国市場の名目GDPに対する時価総額の比率は98~17年の平均値で130.4%だ。
同比率は99年末で172.3%がピークになり、リーマンショックの影響等で08年末には78.8%まで低下していたが、その後は大幅に上昇し、今年9月20日時点では179%になっている。ちなみに日本のバブル相場のピークとなる89年末では147%になっており、現在の米国株はそれを大幅に上回る水準だ。株式市場は「常に新しい事態との遭遇」になるが、今後の投資戦略を考える場合、対GDP比で米国株は過去にない高水準だという事はリスク要因として留意すべきであろう。
ここで、「長短金利の逆転が、株価のピークに先行する期間」に絞って再考した場合、第9波動は、長短金利逆転88年12月、株価ピーク90年7月、金利逆転の株価ピークへの先行期間は「1年7カ月」になっている。同様に第10波動では、00年2月、00年3月、「1カ月」。第11波動は、05年12月、07年10月、「1年10カ月」と各波動によって長短金利逆転と株価ピークの時期は大きく相違している。
この要因としては景気拡張期間が第9、92カ月、第10、120カ月、第11、73カ月となっており、景気拡大がより長期化した第10波動の場合、景気が伸びきったゴムのようになっていた事から、第9・11波動よりも金利の上昇に対する経済の耐久力が弱くなっていたと思われる。それにより景気後退が早まると株価が予見して、長短金利の逆転の1カ月後に株価は天井を付けたと予想される。景気拡大が130カ月を超す可能性のある今回のケースでは、米国の2年国債と10年国債の金利の逆転が本格的な下落相場の『きっかけ』、最大のシグナルになると考察したい。
(北川 彰男)