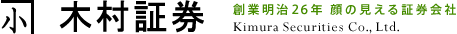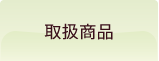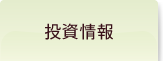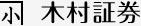FRBのゼロ金利政策の解除時期 (2014年9月版)
年後半から来年にかけて世界の株式市場の大きな注目材料の一つが米国の金融政策を担う連邦準備制度理事会(FRB)の動向であろう。FRBが国債などを大量に買い付ける量的金融緩和と呼ばれる金融政策は今年1月より縮小に入っており、10月には終了する見通しになっている。問題はゼロ金利といわれる現状の政策金利(FFレート)をいつ引き上げるのかが、焦点になると思われる。
今後の金融政策を遂行する上で何が重要なのか、過去の事例を参考に考察したい。コナンドラム(謎)とは2005年2月16~17日、当時のFRB議長であるグリーンスパン氏の上院での議会証言で発せられた言葉である。04年6月30日にFFレートは1.0%から1.25%に引き上げられ利上げがスタートしている。前述の議会証言の時点でFFレートは2.5%になっており、政策金利は引き上げ開始時から1.5%も引き上げられていた。
これに対して米国の10年国債流通利回りは利上げ開始前の04年6月14日時点の4.877%から、05年2月16日には4.156%と0.721%も低下している。金融の常識では政策金利を引き上げて10年国債利回りが低下する事は異常であり、グリーンスパン氏はその原因を明白に言及する事もなく、これを謎とのみ表現していたのである。この謎の正体とは何であったのか。
03年以降、新興国の経済成長率が加速し、世界に多数の成長国が出現している。グローバルなマネーの回転速度が上昇する事で金融の信用創造が拡大し、それがマネーサプライの急増、世界的な余剰マネーの大量発生を誘発したと推察している。その余剰マネーは、新興国の政府の財産保全に対する国民の根強い不信感などの要因もあり、労働生産性が高く財産保全の法律が整備されている米国に世界のマネーが集中したと思われる。国債の金利はどのような理屈を言っても買う人が多ければ債券価格は上昇し、金利は低下する事になる。
これにより、FRBが政策金利を大幅に引き上げても長期金利は低下する前述の謎の状況が生まれたと思われる。超低金利の長期化は米国の家計の過剰消費を促進し、住宅バブルを助長したといえる。過剰消費は米国の経常赤字の肥大化をもたらし、06年には同国のGDPに対する経常赤字比率は過去最悪の5.8%まで拡大している。米国の経常赤字の拡大はドルの信認を揺るがす事態に発展するとして、有識者から1980年代後半より懸念されていた事だ。政策金利を引き上げても長期金利が低下する金融市場の発する警戒信号に対して、議論を深めなかった当時のFRBのわずかな油断が08年9月に発生したリーマンショックという大きな経済的悲劇を引き起こす要因の一つになったと推察したい。
FRBは米国の政策金利であるFFレートを03年6月に1.0%(1958年7月以来の低金利)まで引き下げたのち、04年6月より毎回のFOMC(連邦公開市場委員会、FFレートの誘導目標など金融政策を議論・決定する機関)で17回連続、0.25%ずつFFレートを引き上げて、06年6月に同レートは5.25%%まで引き上げられている。
当時の金融政策を主導したFRB議長のグリーンスパン氏は市場との対話を重視した名議長として高い評価を得ていた。これは結果論になるが、FFレートを引き上げても長期金利が低下する新たな時代に対応するためには『謎』などという言葉で市場をけん制しているのではなく、市場の予想を上回るような利上げのペースを実施すべきであったと思われる。その時点では批判を浴びても、それが経済の円滑な発展に寄与したとみたい。
現在もFRBが量的金融緩和を縮小しているにも関わらず米10年国債利回りは昨年12月31日の3.03%から現状は2.4%前後で推移しており、05年と同じような状況になりつつある。短期的には相場の波乱要因になるが、FRBは過去の失敗を教訓に量的金融緩和の終了後は必要性が低下しているゼロ金利だけは早めに解除したほうがよいと思われる。それは長期的にみれば世界の経済や株式市場の安定した成長にプラスになると推察している。
(北川 彰男)