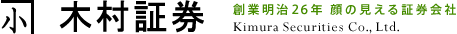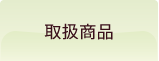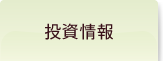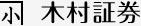生産性の向上 (2022年9月版)
米FRBの利上げ余地を見極めながら、日米の株式市場は、戻りを試す展開を続けている。年後半に向け、景気指標の発表を見極めつつ上値追いの展開を期待したい。
前号の続きとなるが、日本経済の低成長の底流には、少子高齢化による労働力不足の問題が存在する。今後は、少子化をくい止めるか、もしくは労働力不足を生産性の向上で補うかが日本経済にとって必須となる。
IMF の試算による日本の一人あたりの GDP は、1988年の2位から2021年には28位へと大きく後退した。 2017 年後半以後は悪化を続けており、「ジャパン アズ ナンバーワン」と称賛された過去の栄光も今や遠い昔となっている。
「一億総活躍社会」をめざし2018年に施行された働き方改革は、働く人々がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会の実現が目標である。しかしながら、4年を経過した今、生産性の側面からは改善したとはいえない状況が続いている。2020年の日本の一人あたりの労働生産性(就業者一人あたりの付加価値)は、78,655㌦で OECD加盟38カ国中28位、G7の中では最下位である。英国(19位)や韓国(24位)より低く、1970年以降で最も低い順位となっている(2021年日本生産性本部調べ)。労働時間は、以前に比べて短くなったとはいえ、世界的にはまだ長く、付加価値を生み出す力はついていないと考えられる。
今回、物価対策のひとつとして、賃上げが注目を浴びている。先日の厚生労働省審議会では、今年度の最低賃金の引き上げについて、全国平均31円の引き上げが目安として示された。しかし、賃上げ実施後に、企業側が労働コストを価格転嫁すれば物価も上昇することとなる。単なる賃上げのみの政策にとどまれば、実質賃金が押し上げられるのか不明である。今回のインフレは、国内需要の過熱によるものではなく、輸入物価上昇を主因としており、実質賃金は減少しやすい。賃上げをしても、物価上昇によって実質賃金が増加しにくい場合、ミクロの視点では合理的でも、合成されたマクロの世界では、必ずしも好ましくない合成の誤謬のような結果が生じる可能性も否定できない。そのためにも、賃上げと同時に労働生産性の向上が必要と考えられる。
主要国においては労働時間の減少が労働生産性の上昇をもたらすことは同じだが、日本の場合、就業者の高齢化や人口減少でデジタル化への対応遅れや投資抑制を招き、生産性の伸びを鈍化させていると推察される。勤労者 1 人当たりの生産量を増やし、1 人当たり人件費に対する生産物が増える状態にすれば、付加価値額は増える。付加価値額の増加は、1 人当たり賃金の上昇にもつながり、労働生産性上昇=実質賃金上昇率の公式が成り立つ。生産物価の据え置きが前提ではあるものの、労働生産性を引き上げながら、賃上げをすることが実質賃金を増やすためには重要である。
付加価値の上昇には、技術進歩や生産の効率化といったTFP(全要素生産性)の上昇が重要とされる。TFP の上昇をはかるには、情報化投資、研究開発、能力開発などの無形資産への投資が必要といわれている。しかし、厚生労働省の調べでは2010年以降、殆どの産業で一人当たり能力開発費等は伸び悩んでいる。
一般的に従業員の能力を高めるには、定期的研修やスキルアップをサポートする制度の導入、限られた時間の中で成果をあげるという意識を持たせる機会や、労働生産性を向上させることの重要性を伝えることが大切とされる。また、ICT(情報技術)をはじめとしたIT技術の積極的活用により、業務の効率化や内容の可視化をはかることで生産性向上に役立つといわれ、技術活用のための環境整備やスキル向上のための取り組みへの投資が不可欠である。コロナ禍では、デジタル化をテコに、企業の生産性を高めるDX 化が注目されている。今こそ、生産性向上のための仕事のプロセス自体の見直しや、成果の追求を重要視すべきである。
そんな中、海外から押し寄せるインフレに対し、負担増を吸収しきれない状況に陥りつつある。国民生活を豊かにするには、人口減少をカバーするための生産性上昇が不可欠である。一時的な賃上げで良しとせぬようにしたい。
(戸谷 慈伸)